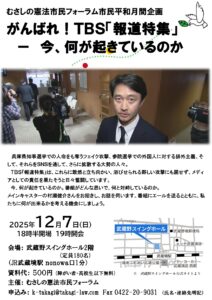地方議会のなり手不足解消は?~全国市議会議長会フォーラムに参加しました

会場の札幌文化芸術劇場hitaruは、9階建ての複合施設。巨大な吹き抜け空間が印象的な建物でした。
8月27~28日、全国市議会議長会研究フォーラム@札幌市に参加しました。
メインテーマは「なり手不足」。市民との対話に全力をあげ、定数削減と報酬引き上げを目指している長野県岡谷市の事例。「鹿児島県の女性議員を100人にしよう(実現できたそうです!)」ライフワークとして取り組んでおられる南さつま市の平神純子市議。おらがまちの議員としてエネルギーに満ちた発表が相次ぎました。
「退職金なし。社会保険なし。期限付き。」議員の仕事をハローワークで表現したらこうなります。これでなり手が増えるでしょうか?とのコーディネーからの投げかけには、どっと笑いが起きました。(笑いごとじゃないんですけどね)
社会全体での「働き方改革」が注目を集めている中、議員の働き方の現実がほとんど有権者に知られていないことが、本当の課題だと感じます。生活者ネットワークの議員は、議員の報酬のうち、半額以上を寄付して市民活動にあてており、確定申告の際の収入額と実態に乖離があるわけで、この実態はさらに!さらに!有権者には知られていません。
フォーラム全体は、(予想通り?)男性割合が非常に高く、保守的な雰囲気。女性参加者は1割程度か? 私が過去に参加した「市民と議員の条例づくり交流会議(自治体議会改革フォーラム)」や「ローカルマニフェスト推進連盟」「全国研究集会(虹とみどり自治体議員情報政策センター)」などの全国集会は有志による手弁当の会議と、今回のフォーラムとの違いはゆっくり分析が必要かもしれません。会場ロビーでは、北海道の地元産品直売ブースが20以上。呼び込みパワーに圧倒されました。
1日目のパネルディスカッションで印象に残ったのは牧原出さん(東京大学先端科学技術研究センター教授)の発言。デジタル化不可避の将来像を見据えて、30年後の生活と行政を組み立てていくべき。なり手リクルート、という直近の対症療法をこえて、「生活をよくするために地方議員が何をすべきなのか」「どうやって議会と議員が機能していくのか」「住民と行政と議会・議員が対話をしていくことの意義」を強く訴えられていました。
山下節子議長会副会長(山口県宇部市議会議長)のきっぱりした発言も、私とは反対の意見でしたが耳に残りました。「若い世代からも議員に手を挙げられるよう、被選挙権の年齢を引き下げるべき、という議論があるが、自分は違う。地方議員という立場は一定の人生経験や良識が求められる存在だ」 会場の一部から拍手が起こったことでもわかるように「人生経験も社会人経験も乏しい若い世代に、議員を任せるわけにはいかない」という自負と本音が垣間見えました。「よくぞ言ってくれた」との心の声が聞こえてきそうでした。
しかし、私はやはり「若い世代が議員になること」は進めるべき。被選挙権の年齢引き下げに賛成したいと考えます。少子化が予想以上のスピードで進んでいる現在、将来を見据えるのであれば、若い世代が「守られる存在」だけでなく「プレイヤー」として社会の担い手となる、ことは必須であると考えるからです。
山下節子さんのご発言は、人口ピラミッドが富士山型だった時代の名残の価値観ではないか? 「釣り鐘型」が進んで「つぼ型」になっている現実をまともに受け止めるのなら、一見良識外れであきれちゃう?と見える若い世代の声も議会に入ってこなくてはいけない。その中で良いものは残る。逆に良識に外れる言動を繰り返す議員がいたら(若くても若くなくても)有権者の目で排除されていく。「良識」は議員の側が決めるのではなく、有権者が決める。という民主主義の原則を根っこに考えなければいけないと感じています。

札幌のシンボル時計台。高層ビルの谷間で写真撮影スポットになっていました。